歯周病についてご存じでしょうか?歯科検診にいくと、歯周病の予防などについてパンフレットなどが置かれていたりします。
歯周病は歯を支える組織である歯肉などが炎症を起こし、徐々に溶けていく恐ろしい病気です。
初期症状は軽く自覚症状がないため、気づかないうちに進行し、重度の症状につながることがあります。
今回は歯周病の初期症状・なりやすい方・予防方法などについて詳しく解説します。大切な歯を守るために、ぜひ最後まで読んでいただければ幸いです。
歯周病の初期症状

私たちの口の中には約400〜700種類もの細菌が存在します。これらは普段は害を及ぼすことはありませんが、口の中が清潔ではないと致命的な存在になります。
歯ブラシなどによる磨き残しがあると、上記の細菌は徐々に歯垢(プラーク)となり、さらには頑固な歯石になるのです。
これらの細菌が元となり、歯周病を進行させる毒素を出します。歯周病が進行すると、炎症が歯肉だけに止まらず、歯を支えている歯槽骨にまで広がり、重度に進行すると歯が抜けることもあります。
そのような歯周病について、ここでは初期症状がどのようなものか解説しましょう。冒頭でも触れたように、歯周病の初期症状は気づきにくいのが特徴です。
しかしこの段階で手を打てれば、健康な歯を守る上で非常に有効だといえます。ぜひ初期症状の特徴を抑え、適切に対処していきましょう。
歯茎の腫れ
歯周病の初期症状の1つに、歯茎の腫れがあります。歯茎が腫れることで歯と歯茎の間に隙間ができるため、食べかす・細菌がたまり、炎症を引き起こします。
歯肉に限局した炎症から、歯周組織にまで炎症が波及したのが歯周炎です。歯周炎になると先述したように、歯茎の奥の歯槽骨まで破壊され歯が抜けることにつながる可能性があります。
歯槽骨とは、歯がはまり込む顎骨を構成している部分で、歯茎の下にあります。これら歯槽骨が破壊されると、どんどん歯が抜けやすくなっていきます。
歯茎の赤み
歯周病の初期症状で見られる現象には、歯茎の赤みもあります。一般的には、健康な歯茎はピンク色で締まりがある状態です。
しかし歯周病が進行すると歯茎の色が徐々に濃くなります。この段階でも痛みはほとんどなく、歯周病の症状だと気づかない方が大多数です。
歯茎からの出血
歯茎からの出血は歯周病の初期症状です。歯を磨いたり歯間ブラシで歯周ポケットを掃除すると、歯茎から出血することがあります。
この出血は、歯茎の炎症が進行していることを示しています。しかしこの段階でも痛みはほとんどないほか、歯茎の出血は多くの場合、軽視されがちです。
健康的な歯は歯ブラシ程度では出血しません。そのことを念頭に置いた上で、自分の歯を磨くときなど、日々チェックするように心がけましょう。
歯周病が進行したときの症状

ここからは、歯周病がより進行したときの症状について解説します。
歯周病が進行すると、歯周ポケットの深さや歯茎の赤みなど、目に見える症状の特徴がさらに明確に現れてくるのです。
これらは黄色信号に当たります。このシグナルを見逃さず、歯周病が手遅れになる前に早期発見できるよう心がけましょう。
歯周ポケットが深くなる
歯周ポケットとは、歯と歯茎の隙間のことです。歯周病が進行すると歯周ポケットが深くなってしまいます。
歯周病ポケットが深くなると、歯垢・歯石がたまりやすくなり、さらに炎症を起こす可能性が高まるという悪循環につながるのです。
また、歯周ポケットが深いと菌が隙間で繁殖しやすい環境ができてしまうため、歯周病の進行に拍車をかけてしてしまいます。
歯茎の赤みが強くなる
歯周病が進行すると、歯茎の炎症が強くなります。そのため、歯茎が赤く腫れ上がってしまうのです。
初期症状では少し赤みがある程度でしたが、歯茎が赤く腫れ上がっている状態になると、歯周病が進行していることのサインといえます。
また、上記で触れたように、歯周ポケットが深くなっていると歯垢・歯石が歯肉の内側にたまり、歯茎の炎症を悪化させることがあります。
これらの症状は目に見える明らかな歯周病の兆候なので、見逃さずにこの段階でしっかり対処しましょう。
歯周病の重度の症状

冒頭でも触れたように、歯周病の初期段階などでは痛みがほとんどなく、気づきにくいのが特徴です。
しかし歯周病が重度に進むと、すでに多くの歯肉・歯周骨などを破壊している場合が多く、かなり重症になっているケースが少なくありません。
ここでは歯周病の重度の症状について解説します。このような状況に陥らないための戒めとしてこれら症状を理解していただければ幸いです。
口臭・口内のネバつき
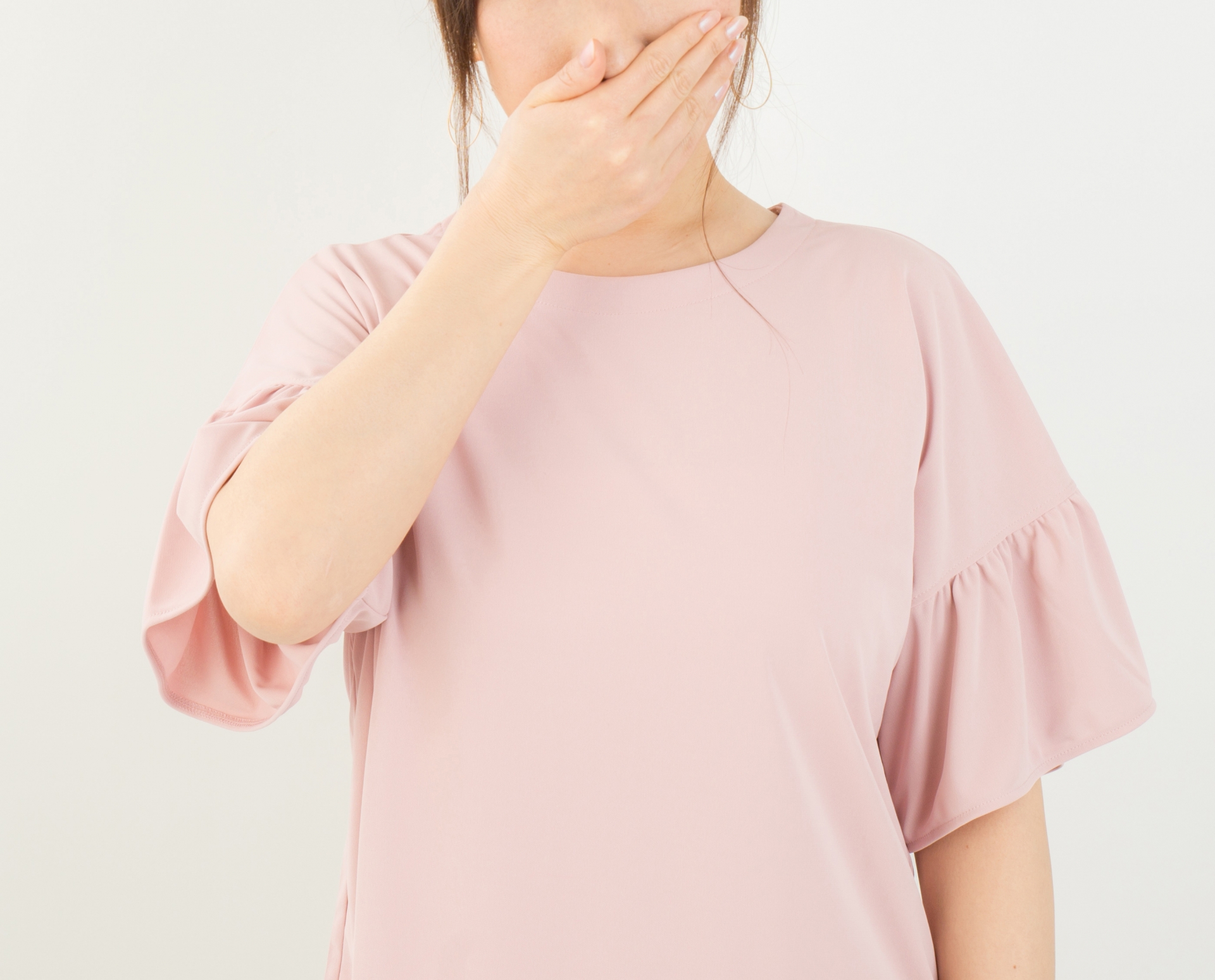
歯周病が進行すると口内環境が悪化し、口臭・口内のネバつきにつながります。このような症状は歯垢・歯石に含まれる細菌が繁殖することによって引き起こされるのです。
冒頭で触れたように、口の中にはたくさんの細菌が存在します。口内環境が清潔でないと細菌は徐々にネバネバした物質を作り出し、歯の表面に付着するのです。
これが歯垢(プラーク)の正体です。歯垢に含まれる細菌の多くは、歯周病を引き起こす細菌だと知られています。
朝目覚めたときに口臭や口内のネバネバが気になる場合は要注意だといえるでしょう。
歯にグラつきがある

歯周病の重度の症状には、歯のグラつきも挙げられます。歯周病が進行しすぎると歯を支える歯槽骨が破壊され、歯の根本の地盤が不安定になるのです。
歯槽骨は歯や歯茎を支えるために重要な役割を果たしており、歯周病によって破壊されると歯がグラついたり、最悪の場合は抜け落ちたりする可能性もあります。
この段階まで歯周病が進行すると、歯茎を自然治癒するのは残念ながら難しいです。そのようにならないためにも、日頃から歯や歯茎の状態をチェックしましょう。
歯が長くなったと感じる

歯周病が重度に進行すると、歯が長くなったと感じることがあります。これは歯周病の炎症により、歯茎が下がることによって起こる現象です。
歯茎が下がると徐々に歯の表面が露出していきます。歯が露出することで、知覚過敏や根面カリエス(う蝕)なども起きやすくなります。
また、すでに述べたように、歯と歯茎の間の隙間は菌が繁殖しやすい環境です。これらの細菌が、歯周病をさらに悪化させる原因となります。
歯が長くなってしまった場合は、歯科医師に相談することが重要です。歯周病の進行を止め、歯肉の再生治療や歯肉移植で隙間を埋める治療などが行われます。
上記のような症状にならないためにも、日頃から口腔ケアを徹底し、定期的に歯科医院で検診を受けることをおすすめします。歯周病の予防にもつながるはずです。
歯周病になりやすい方

前のセクションまでは歯周病の各フェーズにおける症状を解説してきました。ここではどのような方が歯周病になりやすいのか解説します。
自分自身がその特徴に当てはまるかどうかチェックすることで危機感も変わってくることでしょう。
もしも下記の特徴に該当する場合は、日頃の口腔ケアや定期検診をなおのこと真剣に受け止めて生活を改善していく必要があります。
糖尿病の方

歯周病は「糖尿病の第6の合併症」といわれています。糖尿病になると唾液の分泌が減少するほか、唾液中の糖分が多くなります。
この状況は細菌が増殖しやすい環境です。また、糖尿病の方は免疫機能が弱まるため、口の中の歯周病菌に感染しやすい状態といえます。
そもそも糖尿病は血糖値が高い状態が続くことで、血管・神経に悪影響を与える病気です。実は歯周病も糖尿病と同様に血管・神経に悪影響を与えます。
歯周病による炎症が進んだ歯肉では歯周病菌が血管中に入りやすくなります。侵入した菌は内毒素となり、血糖値のコントロールを妨げてしまうのです。
まさしく、糖尿病と歯周病は相互に悪影響を及ぼし合っており、負の連鎖が生まれる合併関係にあるといえます。
妊娠中の方

妊娠中の方も歯周病になりやすいといわれています。その特徴は、妊娠性歯肉炎とも呼ばれます。
妊娠中はホルモンバランスが変化することで歯周病菌の増殖・歯茎の腫れなどを誘発する傾向があるのです。その結果、歯周病になりやすくなります。
また、妊娠中に歯周病を発症すると、早産や低体重児のリスクが高まるとのデータがあります。
これは上記で解説したように、歯周病菌が血管中に入り込むことで胎児にも感染するためと考えられています。
そのため歯周病患者である妊婦の出産は相当なリスクがあると考えられているのです。そのリスクは通常の7倍とされており、実にタバコ・アルコールをゆうに超えます。
しかし基本的に、プラークコントロールが適切になされていれば妊娠性歯肉炎は起こりません。起こっても軽度ですみます。
なお、妊娠中は歯科治療が困難だとされています。そのため日頃から口腔ケアを行うことはもちろん、妊娠が発覚した時点で歯科医師の検診を受けるのが望ましいです。
喫煙者の方

タバコを吸う方は特に注意が必要です。喫煙は歯周病の最大のリスクがファクターとなるためです。
喫煙者が普段タバコを吸うとき、ニコチンの作用により歯茎の血管が酸欠状態になりがちです。この状態では歯周病の初期症状である歯茎からの出血が起こりにくくなります。
また、喫煙者は歯の表面にニコチンがつきやすいほか、歯茎の痛みも感じにくくなるため、歯周病の重要な兆候である「歯茎の腫れ」を見逃してしまいます。
このように、喫煙は歯周病の症状を隠してしまうのです。そのため気づいたときにはかなり症状が進行していて、なかなか治りません。
歯周組織の修復も阻害されるので、治療効果も思うように得られません。
さらに悪いことに、ニコチンは体の免疫機能を低下させます。糖尿病の場合と同じく、免疫機能の低下はすなわち歯周病菌への抵抗力がなくなるということです。
歯周病菌への抵抗力がない口腔内では、菌の増殖が野放し状態になります。そのため喫煙者が歯周病を発症するリスクは、非喫煙者より2倍以上高いといわれているのです。
以上のように、糖尿病・妊娠中・喫煙者の方は歯周病にかかりやすい傾向にあります。これらの特徴に該当する方は、今まで以上に口腔内のケアに努めましょう。
歯周病を予防する方法

ここからは、具体的に歯周病を予防する方法について解説します。
結論から申し上げると、歯周病予防で大切なのは主に「徹底的な歯磨き」・「規律のとれた食生活」・「定期的な検診」の3つです。
以下、それぞれ詳しく解説していきます。
徹底的な歯磨き

これまで解説してきたように、歯周病の原因の大部分は歯垢(プラーク)です。歯垢は口の中の食べかすなどが歯の表面に付着して、細菌が繁殖したものです。
歯垢が溜まると歯茎の炎症につながり、歯周病が進行する大きな原因となります。そのため歯周病を予防するためには、歯垢を取り除くための歯磨きが重要です。
歯磨き時に意識したいのが、歯周病ポケットの歯垢をしっかり取り除くことです。
また、歯磨きをするときは歯茎を傷つけないよう、優しく磨きましょう。仕上げにフロスや歯間ブラシを使えば歯垢の大部分は除去できるはずです。
規律のとれた食生活

意外と見落とされがちですが、口の中に入る食べ物は口腔内の環境に大きく関わります。そのため、食生活も歯周病予防には非常に重要です。
ここでは食生活で意識したいことを紹介します。まず大前提となるのがバランスの取れた食事です。
バランスの取れた食事は体の免疫機能を保つために必要です。すでに解説したように、歯周病菌に対抗するには一定の免疫水準が必要となります。
また、抗酸化作用のある食事をとりましょう。ビタミンC・カロテンは抗酸化作用に優れているとされています。
最後に砂糖や炭水化物を多く含む食品の摂取については特に注意しましょう。これらはプラークが付着しやすくなるので、食後は歯磨きを心がけるようにしてください。
定期的な検診

上記で歯周病を予防する方法について述べましたが、最後に要となるのはやはり、歯科医院での定期検診です。これが最後の砦ともいえます。
歯科医院での検診では歯垢・歯石の除去や歯周ポケットの掃除などを行うことができます。歯科医師による定期的な歯のクリーニングは一番の予防といえるのです。
また、歯科医師による口腔内の検診も重要だといえます。すでに解説したように、歯周病は初期症状があまり現れないことが多いです。
しかし歯科医師が口腔内を検診することで早期発見につながり、治療を行うことができます。
定期的な歯科医院での検診には、年に1回以上の受診が推奨されます。ただし、自宅での適切な歯磨きやデンタルフロスなどを使った口腔ケアも必要です。
また、口臭や口内炎など、何か異常があった場合は、早めに歯科医師に相談しましょう。歯周病は適切な予防と治療が行われることで予防することができます。
上記で解説したような歯周病を発症するリスクが高い人は特に自宅での歯磨きや口腔ケアをしっかり行い、定期的な歯科医院での検診を受けるようにしましょう。
まとめ

この記事では歯周病の初期症状・なりやすい方・予防方法などについて解説しました。
歯周病は大人でありながら歯が抜けてしまう大変に恐ろしい病気です。しかしながら早期発見をするのが大変に難しい病気でもあります。
今回紹介した方法で適切に予防し、歯科検診でしっかり診てもらいましょう。
参考文献
